開教百年目の霊界物語
「聖師を救世主とは言わない」という約束が、戦後、昭和二十一年の愛善苑発足時にあったことを教学委員であった土井靖都氏が書き残しておられる。
万教同根、人類愛善を旗印に再出発した大本であるが、その後の歩みは不可解なところが多い。しかし、「聖師を救世主とは言わない」という約束、つまり「聖師の御神格を隠す約束」をキーワードにたどっていくと、戦後の不可解な大本の歴史をよく理解することができる。
「昭和二十一年愛善苑として立ちあがりし当時より、聖師御昇天の時までは、救世主と云う事も申すなと云う事であり…」
(昭和二十九年十一月六日「総長御宣述に対する疑義」教学委員 土井靖都)

〇事件解決奉告祭「挨拶」の不可解さ
「約束は愛善苑立ち上がりから」とあるが、愛善苑発足前年の昭和二十年十二月に行われた大本第二次事件解決奉告祭での出口伊佐男氏の挨拶に、すでに「聖師を救世主と言わない約束」が反映されていると見る方 が、挨拶の不可解さに納得がいく。
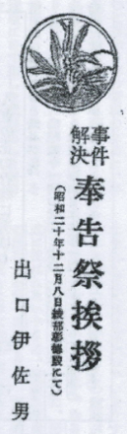
創刊号 抜粋
その挨拶文が愛善苑の機関誌『愛善苑』創刊号に掲載されている。まず不可解なのは「事件の非は我 々にあった」【註1】と言っていることである。奉告祭以前の九月八日の大審院の判決で、大本は治安維持法が無罪となり「事件の非は弾圧側当局にあった」と判断されているにもかかわらずである。
さらに不可解なのは、当局の拷問により十六名にも及ぶ多数の獄中死やその関連死の方々がいるのに、これを悼む言葉が全くないことである。帰幽された方々について「事件中すでに亡くなられ」【註2】との表現があるが、獄中死の方々もこの中に含まれざるを得ず、ずいぶん思いやりのないことである。
また、もっと不可解なのが、聖地を不法に破却、処分した当局【註3】に対して「御理解と絶大なる御好意で、無条件に返還していただいた」と丁寧に礼を述べている【註4】ことである。
【註1】事件の非は我々にあり
「私どもの不注意の為に事件が起き」「私どもに注意の足りなかつた所があった」「弾圧に対し当局を恨む気持は毛頭無い」「他を責めるよりも深く自らを省みなければならぬ」
【註2】 獄中死には触れず
「十年間の事件中すでに亡くなられ今日この喜びをともに迎へることの出来なかった関係の人々たち、その他多くの祖霊様をお慰め申したい」
【註3】詳細 大本七十年史下巻四三二~四四八頁
【註4】警察と町へのお礼
「樋ノ本綾部警察署長さん等の御尽力と赤見坂町長さんら…の御理解と絶大なる御好意により…綾部神苑…無条件返還して頂く」
(出口伊佐男氏挨拶『愛善苑』創刊号)
これらは、当局に対する明らかな「へつらい」と見るべきである。治安維持法が晴れて無罪となったのであるから「非は当局にあった」と言い、また、聖師が救世主であることを堂々と述べればいいはずである。ところが、挨拶には救世主の「救」の字もない。しかも「事件の非が我々にあった」ということは、結局「救世主たる聖師に非があった」ということになってしまう。
しかし、この奉告祭の段階において、すでに「聖師を救世主とは言わない」という約束があり、加えて、当局に対して、どうしてもへりくだらざるを得ない「何らかの理由」があったとすれば、こういう「へつらった」挨拶も理解できない訳でもない。なぜ聖師の神格を隠し、なぜこうも「へつらう」必要があったのだろうか。
〇事件解決奉告祭での聖師の沈黙
また、特徴的であるのが、奉告祭で聖師が終始沈黙されていたことである。聖師は天津祝詞の先達をされただけで挨拶はされず、伊佐男氏の挨拶が終わると、黙ってお辞儀をされただけである。また、伊佐男氏が挨拶をされることを告げられたのも二代様である。
「出口先生は起上つて、黙つてたゞお辞儀をせられた」 (『愛善苑』創刊号一五頁)
なお、奉告祭当日、朝から聖師が言葉少なであったことを、山水荘で面会をされた当時十五歳の牧野八郎氏も覚えておられる。
ところで、この事件奉告祭以前にも聖師の沈黙が二回あるという【註5】。一回目は、大正五年九月、神島で聖師がみろく様の御霊であるとの神示が出た時で、聖師は綾部出発より四日間沈黙されている。また二回目は、昭和七年四月、出口日出麿先生を立てて、聖師に引退を迫る大島豊氏らの動きがあった時で、聖師は十五時間沈黙され、春の大祭も欠席されている。

「未申の金神どの、素盞嗚尊と小松林の霊が、五六七様の御霊で」
(『大本神諭』大正五年旧九月九日)
東京の大島豊氏とひ来たり色々話してゆきにけるなか (『壬申日記』 昭和七年四月十二日)
聖師の二回のいずれの沈黙も、聖師の御神格に関わる中でのことである。「私の神格を悟れ」との沈黙であったのか。さて、奉告祭での聖師の沈黙を我々はどう受け止めればいいのだろうか。
【註5】出口三平氏(平二八・九・一一
東方弥勒主会勉強会「沈黙から再現する神」)
しかし、その後の聖師はけっして沈黙のままではない。聖師は報告祭を終えるとすぐの十二月十日、鳥取吉岡温泉へ立たれ、「軍備撤廃により平和が来る」との強いメッセージを「吉岡発言」【註6】として、新聞を通じて社会に発しておられる。
これは、有形無形の障壁の撤廃という霊界物語の教え【註7】そのままのことであり、また、戦後愛善苑出発の旗印「万教同根」「人類愛善」は、その教えの具現化と言えるのではないか。
なお、吉岡発言自体は『愛善苑』誌創刊号等に掲載はないが、聖師の吉岡温泉行きは記されている(創刊号十六頁)。また、『愛善苑』誌昭和三十七年五月号の伊佐男氏の文章「大本教義と平和憲法」の中で、この吉岡発言がそのまま引用されている。
【註6】 吉岡発言

「いま日本は軍備はすっかりなくなったが、これは世界平和の先駆者として尊い使命が含まれてゐる。本當の世界平和は全世界の軍備が撤廃したときにはじめて実現され、いまその時代が近づきつつある」
(『朝日新聞』昭和二十年十二月三十日)
【註7】霊界物語 障壁の撤廃
「先づ第一に神の子神の生宮たる吾々は、世界にあらゆる有形無形この二つの大なる障壁を取り除かねばなりませぬ。有形的障害の最大なるものは対外的戦備《警察的武備は別》と国家的領土の閉鎖とであります。又無形の障壁の最大なるものとは、即ち国民及び人種間の敵愾心だと思ひます。又宗教団と宗教団との間の敵愾心だと思ひます」
(第六十四巻上第五章「至聖団」)
〇当局に憤る聖師・事件回顧歌集「朝嵐」
一方、聖師は、昭和十七年八月に未決を出られてから、当局に対する憤りに満ちた短歌を多く詠まれている。歌集『朝嵐』の事件回顧歌は千六百首にも及び、当局へへつらう伊佐男氏の態度とは真反対である。
事件の違法や当局の聖地売払いの無道などを、聖師は強く非難し、また、拷問による獄中死や関連死の信者十六名を、心から悼んでおられる。

信者一人ひとりの死を丁寧に詠み、あたかもそれぞれの傍らにおられたかのようである。いやきっと、聖師はそれぞれの信者の御霊の傍らにおられ、昇天後の行き先に光を照らしておられたに違いない。
〔事件の違法〕
・リンゴ三個神饌物を頂戴し治安維持法と強いられし月(1312)
・後の世の笑話の種となりぬべし大根芋の無法の公訴は(1325)
・芋坊主五十万円投げ出してデッチ上げたる芋
大根事件(1376) …芋坊主:東本願寺
〔聖地売払いの無道〕
・両聖地を安価で町に売払へと黒犬牙を光らせ迫りぬ(1327)
・解決の付かぬうちより毛物等は月座を破り無道を極めぬ(1389)
〔信者の獄中死〕
・元気なりし岩田は敢えなく身失せけり無法の攻苦に逢ひたる果てを(1305)
・中立売署酷の荒びに堪え切れず首締め上天したる栗原(1301)
・種々の難題と強き拷問に身体いため死したる高木氏(1309)
・悔やみても返らぬ事とは思へども余りの無法に書き留めおくなり(1306)
・長髪を曳き摺りまはしさいなみしいたさに堪へず短髪となり(1290)
(事件回顧歌集『朝嵐』( )内は歌集でふられた番号)
〇悪く言われる伊佐男氏
ところで、聖師の歌の中で伊佐男氏(=宇知麿)を詠んだものは、他と比べて異質である。
〔宇知麿〕
・宇知麿は曲犬どもに噛み付かれ事実無根の告白をなせり(1381)
・宇知麿の自白せしとう聴取書もちて統ての羊の調書作るまが(1382)
歌で「曲犬に噛み付かれ」とあるが、大本七十年史では、伊佐男氏はビンタを二、三回受けた【註8】にすぎず、ひどい拷問は受けていないこととなっている。また、伊佐男氏の「事実無根」、つまり嘘の自白によって、他のすべての信者の調書が作られたこととなっている。
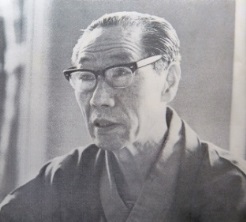
また、伊佐男氏は嘘の自白をした理由について、「死んでしまっては本当のことが言えなくなる」と上申書で述べているが、結局、この伊佐男氏の嘘の自白をもとに作られた他の者らの調書が、みな同じであるという不自然さ【註9】もあって、裁判は無罪へと向かうのである。
なお「伊佐男氏の人差し指が爪の根元近くまで斜めに欠けていたのは拷問が原因」【註10】と伊佐男氏の子、出口和明氏が明らかにしているが、そうするとビンタ二、三回どころではない。

実は、千六百首の事件関連歌のうちの六百首の清書を伊佐男氏が行っている。聖師の思いは痛いほどわかっていたはずである。伊佐男氏の「へつらい」の挨拶は、「忍耐」の挨拶と言うべきかもしれない。ではなぜ、伊佐男氏は、あえて忍耐をしながら「へつらい」の挨拶をしなければならなかったのだろうか。
一方聖師は、伊佐男氏に関して、一見同情感のない歌を詠んでおられるが、何か意図的に悪役に仕立てているようにも感じる。
【註8】「平手で頬を二三度打たれ」「すべてを隠忍していきてゐなければならぬ」
(伊佐男氏上申書:昭一五・一一・一六、「大本七十年史 下巻」四一九、四二〇頁)
【註9】「どの調書もまったく同じことで、これはおかしいと思った」
(陪席判事 田村千代一、同六一五頁)
【註10】「松のひびき」
出口うちまるを偲びて
(出口和明発行 「天声社」一〇六頁)

出口うちまるを偲びて
〇「みろく下生」のない聖師伝
「聖師御昇天まで聖師を救世主とは言わない」とされた約束が、そのとおり昭和二十三年一月十九日御昇天の聖師の葬儀での「誅詞」で実行されている。
普通に考えれば、救世主の御昇天であるから聖師の「誅詞」は、言葉を尽くして御業績を褒め称えたものであることが想像される。しかしそうではなく、聖師の来歴を羅列しただけの誠にあっさりとしたものになっている。聖師を「救世主」とは言い切れず、「救いの君と崇められ」などとぼやかすのが精一杯の表現になっている。
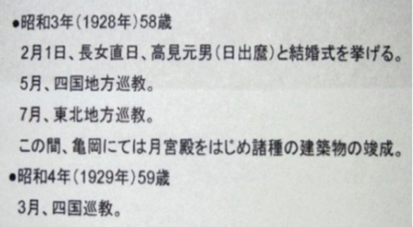
「北の涯の崎々南の海の島々までも御跡至らぬ隈なく或は蒙古の野に雄叫び或は満州の都に遊び 東亜の国々は言うも更なり遠く西の海の彼方の人々にでも救いの君と崇められ」
(誅詞 出口伊佐男斎主)
さて、「聖師を救世主とは言わない約束」は、「聖師御昇天まで」とされていたが、御昇天後も続いた。昭和二十八年四月に天声社から発刊された「聖師伝」には、昭和三年三月三日「みろく下生」の記載がない。
〇「みろく下生」の教典上の根拠
そもそも、天のみろく様が、救世主神・瑞霊神素盞嗚大神と顕現して現界に「下生」されたのが出口王仁三郎聖師である。またその「下生」は、国祖御隠退の時に、天祖・みろく様が国祖とお約束をされ、国祖再出現の折には、天祖が降ってきてお手伝いをされるという「御神約」の実行である。
そして、この下生されたみろく様の御教えにより、松の世、みろくの世が建設されるというのが、大本出現の根本義である。私は、そう信じている。
以上述べたことは、教典の各所に示されている。
まず、天祖たるみろく様が下生され、国祖のお手伝いをされるということについて
「五十六億七千万年の星霜を経て…弥勒の神下生して三界の大革正を成就し、松の世を顕現するため…苦・集・滅・道を説き、道・法・礼・節を開示し」
(『霊界物語』第一巻「発端」)
「現界の不備欠点を補はむが為に大神は自ら地に降り…天界の福音を宣伝し」「弥勒を世に降し…天国の福音を…示させ」
(第四十八巻第一二章「西王母」)
「神諭に『艮の金神が天の御先祖様、五六七の大神様の御命令を受けて、三千世界の身魂の立替、立直しを致すぞよ。それについては、天の神様地に降りて御手伝いあそばすぞよ』とあり」 (回顧録「序」)
とあるとおりである。また、天祖・みろくの大神が神素盞嗚大神と顕現されることについても
「至仁至愛の大神は其神格の一部を地上に降し神素盞嗚尊と現はれ」
(第四十九巻第三章「地鎮祭」)
「坤の金神どの、素盞嗚尊と小松林の霊がみろくの神のおん霊で…みろくさまが根本の天のご先祖さまであるぞよ」
(『大本神諭』大正五年旧九月九日)
と示されている。そして、聖師の御霊が神素盞嗚尊であることを歌で明らかにされている。
わが魂は神素盞嗚の生御魂瑞の神格に充されてあり 〔第四十一巻第十六章「三番叟」余白歌〕
教典をこのように丁寧に探っていけば、天のみろく様が出口聖師として地上に「下生」されたということは明白である。
(令和元年11月23日記)




コメント